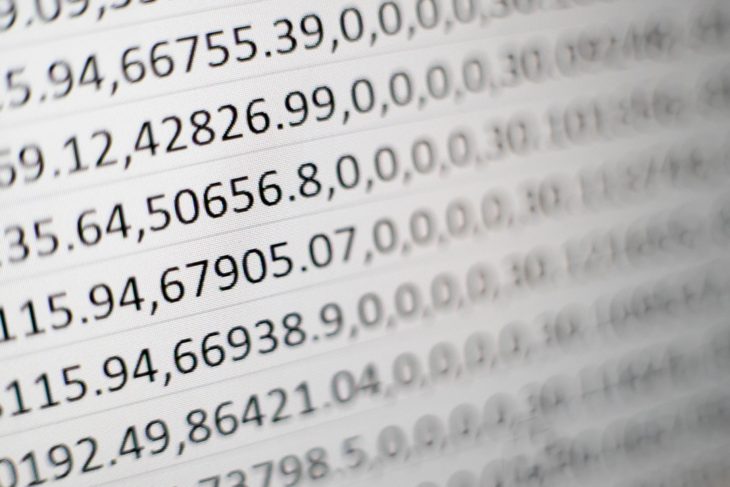ファイナンシャルプランナー3級の合格から期間が空いてしまいましたが、あらためて2級の合格を目指して学習を始めようと思います。
ファイナンシャルプランナーとは
人生の目標を達成するための資金計画を策定する事を「ファイナンシャル・プランニング」と呼び、金融や税制、不動産など幅広い知識を備えて、相談者の目標達成をサポートする専門家のことをファイナンシャルプランナー(以下FPと呼ぶ)といいます。
FP機能検定は、日本FP協会と金融財政事情研究会(きんざい)の二つの団体が実施しています。
団体による試験の違い、2級と3級との違い
FP2級はFP協会、きんざいのどちらからでも受験できます。団体によって受験内容が若干異なるので、2級と3級の違いと合わせてみてみます。
試験範囲
2級と3級の試験範囲は同じです。
B.リスク管理
C.金融資産運用
D.タックスプランニング
E.不動産
F.相続・事業承継
出題範囲の詳細は省きますが、3級との大きな違いとして、2級では法人のファイナンシャル・プランニングが試験範囲に含まれます。
出題形式
団体や級の違いによる出題形式の特徴を下記にまとめてみました。
| 学科 | ||
| 2級 | 3級 | |
| 出題数 | 60問 | 60問 |
| 出題形式 | 四択(マークシート) | 三択、◯×式(マークシート) |
| 実技 | ||
| 出題数 | FP協会 :40問 | FP協会 :20問 |
| きんざい :5題(15問) | きんざい :5題(15問) | |
| 出題形式 | 記述式 | マークシート |
2級の学科試験は四肢択一式で出題されます。実技試験ではFP協会の場合、3級に比べて倍増した40問の出題。
また、両団体ともに記述式の出題で、なかには計算によって数値を問う出題もある為、高難度となっています。
実技試験の出題科目
FP協会の実技試験は1〜3級のいずれも資産設計提案業務が出題科目なのに対し、きんざいは2級以降複数の科目の中から一つ科目を選んだ上で受験します。どの科目を選択するかも重大な選択です。
難易度と合格率
2020年1月に実施された2級試験の合格率をまとめました。
| FP協会 | |||
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 学科試験 | 23,968 | 10,032 | 41.86% |
| 実技試験 資産設計提案業務 | 18,980 | 11,884 | 62.61% |
| きんざい | |||
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 学科試験 | 40,110 | 11,557 | 28.81% |
| 実技試験 個人資産相談業務 | 20,294 | 6,724 | 33.13% |
| 中小事業主資産相談業務 | 1,745 | 974 | 55.81% |
| 生保顧客資産相談業務 | 10,455 | 4,797 | 45.88% |
表に記してはいませんが、3級よりも合格率はかなり下がります。
学科は四択式出題、実技では記述式になるなど出題形式の変化も影響するでしょうし、そもそも設問自体より深く問われていると思われます。
実技試験では団体によって、合格率が大きく変わっています。FP協会では比較的短い文からなる問いを数多く解くことに重点をおいているようですし、きんざいでは実務的な長文を読み込んだ上で解く内容となっています。
それぞれ、HPで過去問題を掲載しているので、確認した上で受験する団体や実技試験の科目を検討しましょう。
私の勉強方法
2021年1月度の試験を目標に学習を始めます。およそ3ヶ月の期間で150〜180時間の勉強時間を確保できるようにします。
テキストは3級合格時と同様に、TAC出版の「みんなが欲しかった! FPの教科書」「みんなが欲しかった! FPの問題集」を利用します。
一見した所、「3級のテキスト+α」といった感があり、3級で得た基本的な知識に応用的な知識を上乗せさせるようなイメージですが、実際はどうなのか、学習しつつ今後途中経過を記していきたいと思います。